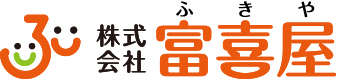ゴールデンウィーク中の5月5日は「鯉のぼり」や「兜(かぶと)」を飾り、子どもたちの健やかな成長や幸せを願う「こどもの日(端午の節句)」ですね。
行事食では子どもたちも大好きな「ちまき」や「かしわ餅」が定番ですが、その意味をご存知ですか?
今回はそんなこどもの日にまつわる話や行事食についてお伝えします。

index
こどもの日( 端午の節句)とは、どんな日? 実は母に感謝する日
5月5日は、古来中国から伝わってきた「端午の節句」にあたります。
古来中国では季節の変わり目である5月は病気や災いが増えることから、邪気を払うとされていた菖蒲(しょうぶ)を用いた行事が行われていました。


門に「菖蒲」を飾ったり、菖蒲酒(しょうぶざけ)を飲んだり、菖蒲の根や葉を入れて沸かす「菖蒲湯」に入ったりするのも健やかな日々への祈りが込められています。
端午の節句が日本へ伝わると、菖蒲が武勇を重んじる「尚武(しょうぶ)」と同じ読みであることから、やがて武家の男子の成長と健康を祝う日へと変わってきたとされています。
1948年(昭和23年)になると祝日法によって5月5日は、「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。」日として、祝日になりました。
つまり、子どもの日は、子どもたちの健やかな成長を祝うと同時に、母にも感謝する日だったのです。
まるで、子どもたちの生の源である母への愛情と感謝のメッセージが込められているようですね。

知っておきたい!こどもの日に楽しむ行事食とその意味について
とはいってもこどもの日(端午の節句)のお祝いは子ども主体が一般的です。ここでは、こどもの日の行事食をいくつかご紹介させて頂きますね。
- ちまき(粽)
葉をむく瞬間が楽しみにもなるちまき。もともとは笹の葉ではなく茅(ちがや)の葉でまいていたので「茅巻き(ちまき)」と呼ばれるようになったといわれています。茅は病や災難を払う葉とされていました。 - 柏餅(かしわもち)
柏餅は子どもたちも大好きなおやつのひとつですね。柏の葉は新葉がでるまで古い葉が落ちない性質があることから、「子孫繁栄」を願い、縁起のよい和菓子として人気があります。 - 草餅(くさもち)
ヨモギなどの葉を入れてついたお餅です。古来、香りの強いヨモギのような植物は邪気や魔除けの力があると考えられていました。 - 筍(たけのこ)
たけのこは、成長が早いことから、「たけのこのように早く大きくなってほしい」という願いを込めて食されています。たけのこご飯やお吸い物などにすると、子どもたちも喜ぶことでしょう。 - 魚類(カツオ、ブリ)
カツオは「勝男」に通じて、ブリは成長するにつれて名前が変わることから「出世魚」としてお祝いの日に親しまれています。また、鯉のぼりにかけて鯉なども食べられることがあります。
そのほか、おじいちゃんやおばあちゃんを招いてケーキを食べることもあります。
昔ながらの風習に、その土地や家庭の文化が混ざりあって各家庭の「こどもの日」のお祝いをしているようです。
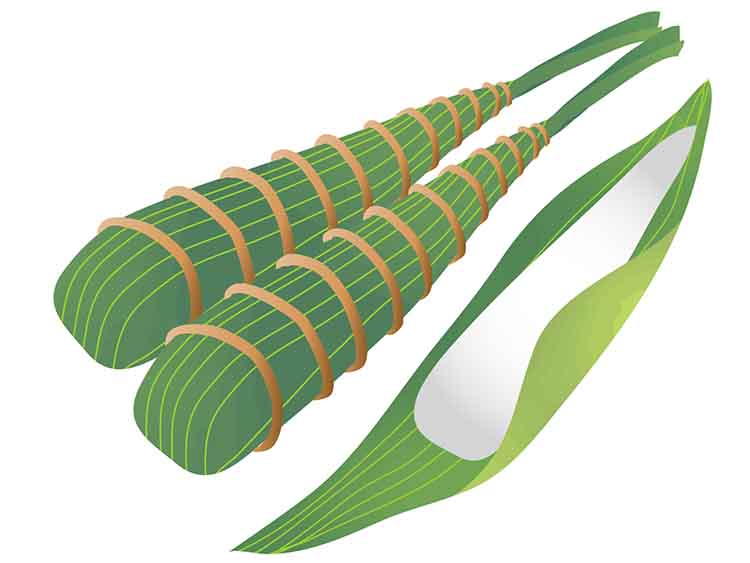
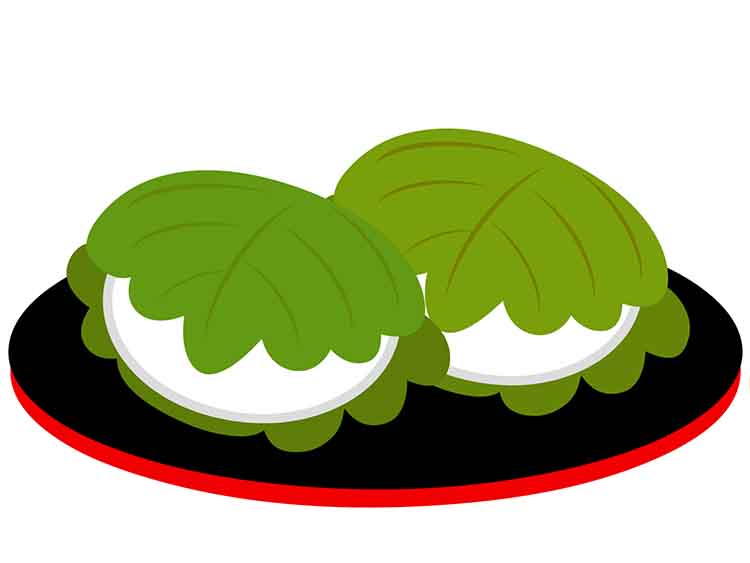
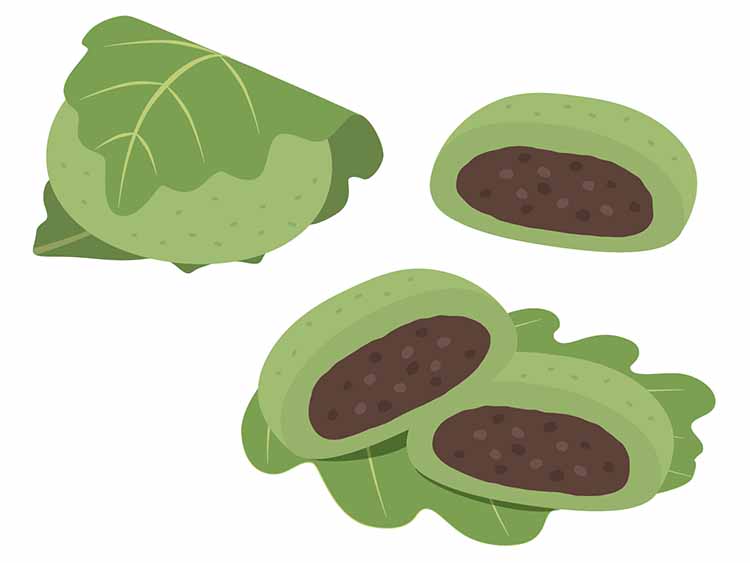

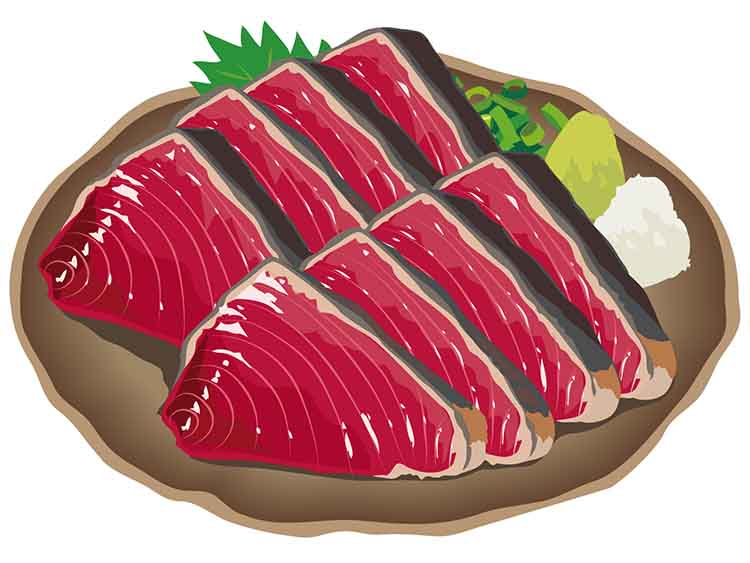

行事の話題が「伝統文化」を大切にする心も育みます
今では伝統行事を家庭で楽しむ機会が減っている傾向がありますが、ちまきや柏餅を食べるだけでも、子どもたちにとって素敵な思い出になります。
ぜひ、こどもの日の由来や行事食の意味に触れながら家族で楽しい日にしてくださいね。きっと、日本の伝統文化を大切にする心も育むことにも繋がることでしょう。
【こいのぼり】の歌を2曲をご紹介! こどもの日にみんなで歌おう!(歌詞付き)
やねよりたかい~ 「こいのぼり」
【作詞:近藤宮子、作曲:不詳】
- やねよりたかい こいのぼり
おおきいまごいは おとうさん
ちいさいひごいは こどもたち
おおしろそうにおよいでる - やねよりたかい こいのぼり
おおきいひごいは おかあさん
ちいさいまごいは こどもたち
おもしろそうにおよいでる - ごがつの かぜに こいのぼり
めだまを ピカピカ ひからせて
おびれを くるくる おどらせて
あかるい そらを およいでる
※3番の歌詞には、いろいろな説があります。一般的なものを載せました。
いらかのなみと~ 「鯉のぼり」 文部省唱歌
【作詞:不詳、作曲:弘田龍太郎】
- いらかのなみ と くものなみ
かさなる なみの なかぞらを
たちばな かおる あさかぜに
たかく およぐや こいのぼり - ひらける ひろき そのくちに
ふねをも のまん さまみえて
ゆたかに ふるう おひれ には
ものに どうぜぬ すがたあり - ももせの たきを のぼりなば
たちまち たきに なりぬべき
わがみに によや おのこご と
そらに おどるや こいのぼり
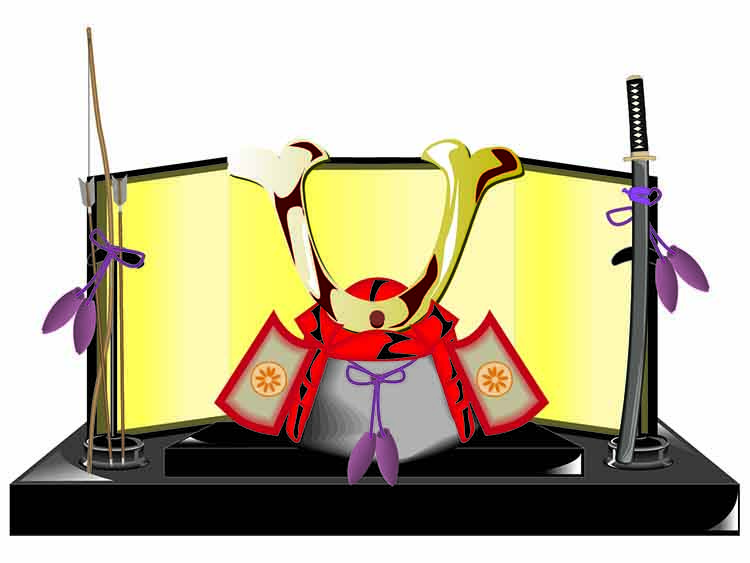



※「季節の行事コラム」は、保育園・幼稚園・こども園で年中行われる季節行事をこどもたちに説明するための解説コラムです。イベントの由来、行事食、歴史など内容を盛りだくさんでお届けしています。
こどもの日 由来 子供向け/こどもの日 保育園・幼稚園/こどもの日 意味/こどもの日 雑学/こどもの日に食べるもの/端午の節句 食べ物/端午の節句 いつ/端午の節句 由来/端午の節句 食べ物/こいのぼりの歌