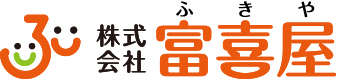『食膳は一汁一菜にせよ』江戸時代、岡山藩主池田光政が出した倹約令の一項です。
困った庶民は、酢飯に魚や野菜を混ぜ込んで「一菜」とすることを思いつきました。これが「ばら寿司」の始まりです。
また、これには岡山名物「ままかりの酢漬け」が乗せられます。関東では「さっぱ」と呼ばれる魚で雑魚扱いですが、岡山では酢漬けや塩焼きにして食べます。
「まま=ご飯」を「借り」たいほどおいしい魚です。
index
『食膳は一汁一菜にせよ』-ばら寿司

「ばら寿司」レシピの材料
材料(米2合分のすし飯)
- 干ししいたけ… 2枚
- 高野豆腐… 1/2枚
- にんじん… 40g
- だし汁… 100ml
- (A) 砂糖… 大さじ1
(A) しょうゆ… 大さじ1
(A) 塩… 少々
ばら寿司(ちらし寿司)のすし飯に混ぜる「具」のつくり方
- にんじんはせん切りにする。
- 高野豆腐と干ししいたけは水につけてもどして食べやすい大きさに切る。
- だし汁と (A) を混ぜて、にんじん、高野豆腐、干ししいたけを入れて煮る。
- 冷めたらざるにあげて水けをきる。
- すし飯に混ぜ、もりつけて好みの具をのせるとばら寿司のできあがり。
「ばら寿司」レシピの調理のポイント
- 「ばら寿司」と「ちらし寿司」の違いは、具材を酢飯に混ぜ込むか混ぜ込まないかです。
・ばら寿司 ⇒具材を小さく切って酢飯に混ぜ込みます。
・ちらし寿司⇒具材を酢飯に「散らして」のせるのが一般的です。 - ばら寿司は素朴な田舎料理ですが、最近では錦糸卵、えびやタコ、絹さや、レンコンなどを具材にして色鮮やかに仕上げる方が増えています。