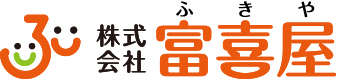こどもにもっと野菜を食べてほしい…。これは、みなさん共通の願いですね。
そんな思いから、ついつい「どうしたらおいしく食べてくれるか?」と味つけや調理方法ばかり工夫していませんか?
もちろん味は大事ですが、実は「知ること」もとても大切なんです。
このコラムでは、保護者の方に野菜への理解を深めていただき、それをこどもに話してあげることで、野菜そのものに興味をもってもらうために楽しいお話を書こうと思います。
これもとっても大切な食育です☺️
野菜っていろいろな分け方ができることを知っていますか? たとえばこんな感じ…
- 春・夏・秋・冬の季節で分ける(旬を知る)
- どの部分を食べているのか?(葉、茎、実などの食べる場所で分ける)
- こども向けの食べ方(料理)で分けてみる
こどもは「わからないもの」には不安を感じるので、知らない野菜はなかなか口に入れてくれません。
逆に「知っている」という安心感があると、「ちょっと食べてみようかな…」と思えるかもしれません。
野菜をただの「食べ物」ではなく、「面白いもの、身近なもの」、また「知りたい存在」なんて思ってもらえたら嬉しいし、大人もワクワクしますね☺️
たとえば…
「オクラは切ると⭐お星さまになるから、お皿の上をお星さまでいっぱいにしよう!」
「ブロッコリーはまだ眠ってるお花(つぼみ)だよ。咲いたら黄色い花になるんだって!」など、大人のちょっとした言葉が、こどもの世界を広げていきます。
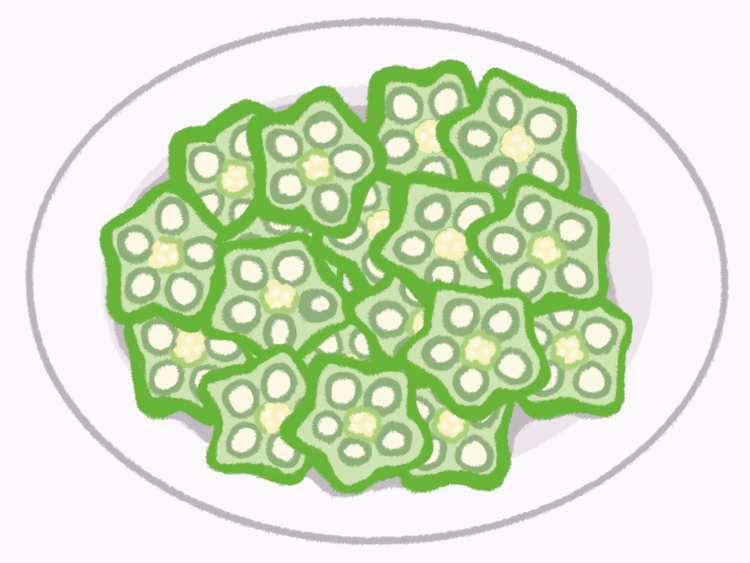
index
春・夏・秋・冬の季節で分ける(旬を知る)
↓ こんなこと思ったことありませんか?
なぜ野菜は、季節ごとに育つものが違うの?
野菜が季節ごとに違うのは、植物の「生きるための工夫」と「気候との相性」が関係しています。わかりやすく整理します。
- 気温と植物には、それぞれ「育ちやすい温度」があり、暑すぎたり、寒すぎるとうまく育たない野菜があります。
トマト、きゅうり ⇒ 暑い夏に強い
ほうれん草、大根 ⇒ 涼しい秋・冬に強い - 植物は「昼が長いと花を咲かせる」「夜が長いと成長する」など、日の長さに反応する性質を持っています。
たまねぎ ⇒ 春に植えて、夏の長い日を浴びると玉が大きくなる
ほうれん草 ⇒ 日が長くなると花を咲かせてしまう(とう立ち) - 雨や水分の量
夏は雨が多いから、たっぷりの水を必要とする野菜が育ちやすい
冬は水が少なくても耐えられる野菜が残ります - 害虫や病気との関係
夏は虫がたくさん出る ⇒ 虫に強い野菜が多い
冬は虫が少ない ⇒ 葉っぱの野菜も育てやすい
などなど… 「気温・日照・水分・虫」など、その季節の自然条件に合った野菜だけが元気に育つんです。
こどもに話して聞かせるなら…
- 🌱 野菜にはね、それぞれ「すきな季節」があるんだよ!
☀️ トマトは、あつ~い夏がすき
❄️ ほうれん草は、ひんや~りした冬がすき - だから季節ごとに、ちがう野菜が元気にそだつんだよ~
こんな感じいかがでしょうか (*ᴗˬᴗ)

春・夏・秋・冬(旬の野菜)
🍀 春(3〜5月)
🌸 あたたかくなって芽が出る季節。みずみずしくやわらかい食感と、独特の香りを感じる野菜が多いです。

たけのこ、そらまめ、アスパラガス、キャベツ、新じゃがいも、新玉ねぎ、菜の花、春キャベツ、スナップエンドウ、たらの芽、ふきのとう、クレソン
👉 新たな生命を芽生えさせる「春の訪れを感じる野菜」




☀️ 夏(6〜8月)
🔥 太陽の光をいっぱい浴びて、色鮮やかでみずみずしい野菜が育つ季節。生で食べられるものが多いです。

トマト、きゅうり、なす、とうもろこし、ピーマン、オクラ、とうもろこし、枝豆、ゴーヤ、
👉 暑さに負けない「元気をくれる野菜」

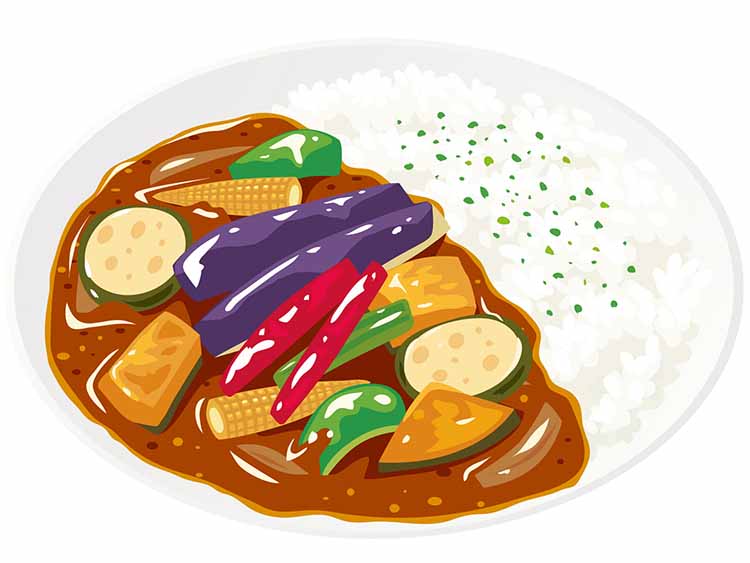

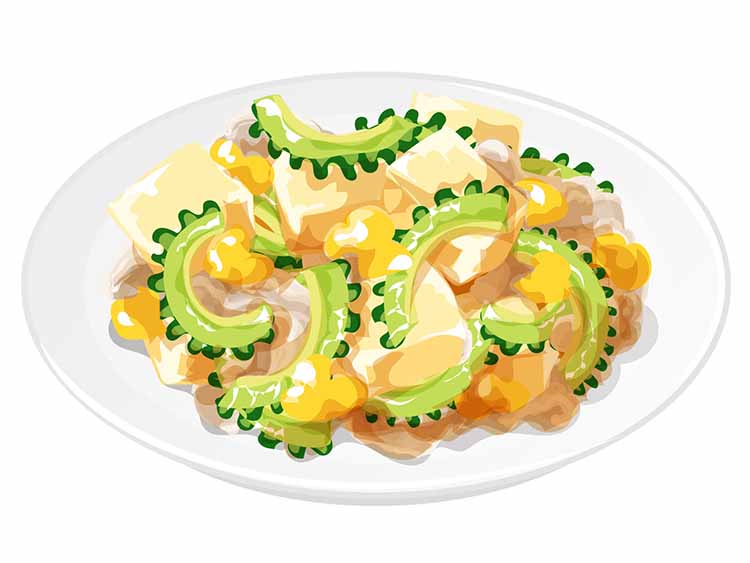
🍂 秋(9〜11月)
🍁 涼しくなり、しっかり実った野菜がおいしい。夏の野菜と比べて水分が少なく、甘みと栄養が凝縮されています。

さつまいも、かぼちゃ、れんこん、きのこ類、さといも、ごぼう(根菜類)や、しいたけ、しめじ、まいたけ(きのこ類)
👉 体をあたたかくする「実りの野菜」




❄️ 冬(12〜2月)
⛄寒さから身を守るために細胞内に糖を貯めるので、あま~くなる野菜が多い。栄養価も高く風邪予防にもなります。

大根、カブ、レンコン、金時ニンジン、ユリ根(根菜類)、白菜、ほうれん草、小松菜、水菜、春菊(葉物野菜)、長ねぎ、ブロッコリー
👉 冬は鍋がうれしい「甘くてほっこり野菜」




🌱 旬(しゅん)ってなあに?
- 「野菜が一番おいしくて、たくさんとれる時期」のこと
- 旬の野菜は、味がよくて栄養たっぷり、しかも安い!
👉 「旬の野菜は、その季節からのプレゼント」です✨
こどもに話して聞かせるなら…
- 🍅 「旬(しゅん)」っていうのは、🌞 野菜がいちばん元気で、おいしい時のこと。
☀️ 夏はトマトやきゅうり
❄️ 冬は大根やほうれん草 - 🍀 その季節にしか食べられない、🎁 自然からのプレゼントなんだよ。
こんな感じいかがでしょうか (*ᴗˬᴗ)







「なんで野菜を食べてくれないの…?」と悩む方へ
最後に、とても大事なことをお伝えします。
まず最初に、
「野菜を食べない」=「ダメ」ではありません。
こどもが野菜を食べたがらない一番の理由は、
好き嫌いではなく、
まだ経験が少ないだけだと、私たちは考えています。
こどもにとって「食べること」は、毎回が新しい体験です。
味、におい、食感、見た目…
大人が当たり前に感じていることも、こどもにとっては驚きの連続。
だから、焦らなくて大丈夫です。

食べる前に、大人ができるいちばん大切なこと
大切なのは、大人が楽しそうに関わること。
- 「これ、どんな味かな?」とワクワクする
- 「おいしいね」と笑顔で話す
- 食卓で会話を楽しむ
こどもは、大人の姿を見て学びます。
「食べるって楽しいことなんだ」と感じられることが、
何よりの食育です 😊
食べる量よりも、
食べる時間の雰囲気を大切に。
ゆっくり、その子のペースで、
“おいしい”を一緒に育てていきましょう 🌱
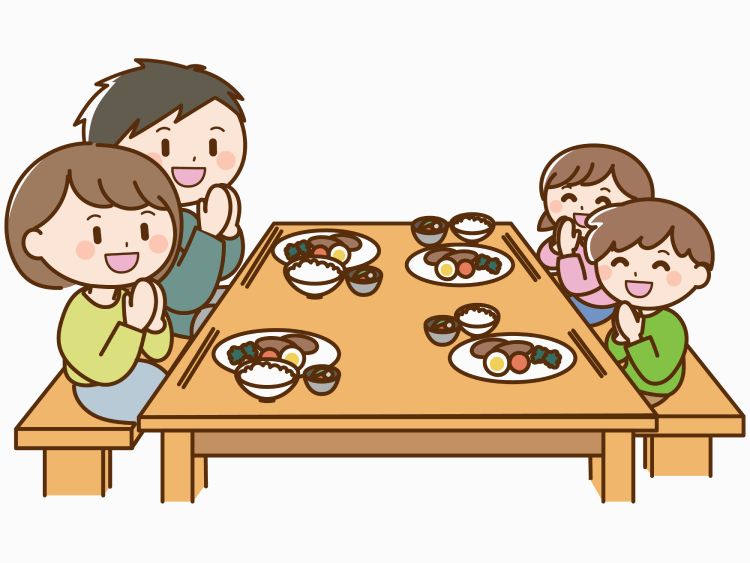
【ご注意ください】枝豆を含む豆類やナッツなど、幼児の窒息リスクについて
「枝豆」には硬さがあるため、誤嚥や窒息の危険があります。
消費者庁では「硬い豆やナッツ類(枝豆・落花生・アーモンドなど)」をはじめ、「ブドウやミニトマトなど丸くてツルっとした食材」、「もちや白玉団子など粘着性の高い食材」、「こんにゃくゼリーのように噛み切りにくい食材」について、幼児には特に注意が必要としています。
なお、給食では、安全のため上記の食材は使用していません。